「ブログはもう稼げない、副業としては時代遅れだ——」
そんな声がSNSや2ch(現5ch)、果ては大手インフルエンサーの間でも聞かれるようになりました。特に、かつて“ブログで稼ぐ”というムーブメントを牽引してきたイケハヤ氏が2025年4月に「ブログで稼ぐ時代は終了」と宣言したことは、大きな波紋を呼びました。
果たしてブログ副業は本当にオワコンなのでしょうか?それとも、まだ戦える土俵は残されているのでしょうか?
この記事では、「ブログ 副業 オワコン」と検索してたどり着いたあなたの疑問に明確にお答えします。
・「ブログは稼げないからやめたほうがいい?」
・「ブログで月1万円稼ぐのは難しいですか?」
・「そもそも、ブログの欠点って何?」
こうした問いに対し、ブログ収入の実態や“月1万円の壁”の真相、個人ブログが生き残るための具体的戦略をもとに徹底解説していきます。
さらに本記事では、「一般人のブログ収入の平均」や「実際に稼げた人と失敗した人の違い」も含めて紹介。
単なる悲観論ではなく、**2025年以降でも通用する“再設計された副業ブログ戦略”**を提示します。
「ブログはオワコンだ」と言われてなお、少数ながら結果を出している人がいるのも事実。
今後も個人がブログで収益を得たいと考えるなら、旧時代の成功パターンにしがみつかず、次世代型ブログ戦略に進化させる必要があるのです。
それでは本題に入りましょう。まずは「なぜここまで“ブログ副業はオワコン”と言われるようになったのか?」その理由を紐解いていきます。
✅この記事を読むとわかること
- ブログ副業がオワコンと呼ばれる具体的な理由
- 2025年以降に個人ブロガーが直面する不利な現実
- ブログで稼ぐための新しい戦略と設計の考え方
- AIやSNS時代に個人ブログが生き残るための条件

⚠️本記事で使用した画像は説明のためのイメージ画像です。実際のデザインとは異なる場合があります。
ブログ副業オワコン時代の現実的な始め方
「ブログ 副業 オワコン」と言われる理由を整理する
副業ブログがオワコンと言われる6つの背景
副業ブログは「もう稼げない」「オワコン」とささやかれるようになりました。その理由は複数存在し、それぞれが密接に関係しています。
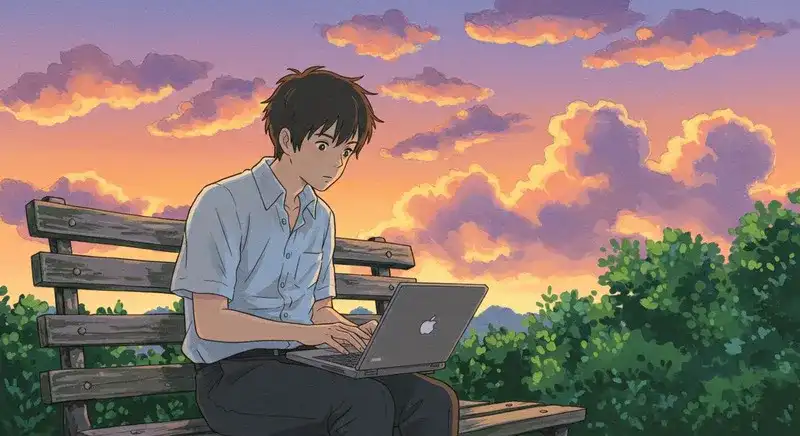
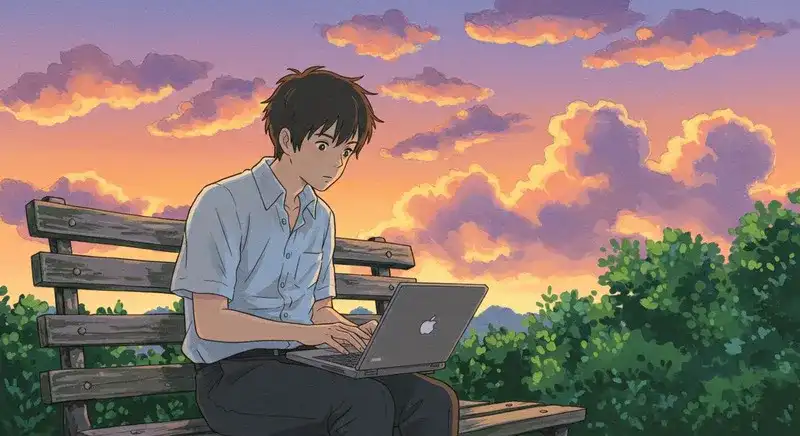
1つ目は「収益化までに時間がかかること」です。副業として始めたものの、半年〜1年経ってもほとんど収益が出ないというケースが珍しくありません。即効性を求める現代人にとって、このタイムラグは挫折の大きな要因となります。
2つ目は「企業サイトの台頭」です。検索結果上位が大手企業に占められ、個人が入り込む余地が少なくなりました。
3つ目は「SEOの難化」。Googleのコアアップデートによって、高品質なコンテンツでないと順位が安定しない状況が続いています。
その他、「ステマ規制」「AIの普及」「動画やSNSの普及」といった変化が、副業ブログにとって逆風となっています。
AI・SNS台頭とテキスト離れの実態
AI技術の急速な進化により、誰でも簡単に文章を量産できる時代になりました。これにより、読者は「情報の質」よりも「情報の鮮度や見せ方」を重視する傾向が強まりつつあります。
一方、SNSやYouTubeといった視覚・聴覚に訴えるメディアが主流となったことで、「読む」こと自体が敬遠されやすくなりました。特に若年層を中心に「動画やショートコンテンツで済ませたい」というニーズが高まっています。
これらの変化は、ブログというテキスト主体のメディアにとって不利な流れであり、「オワコン」と言われる背景にもなっています。
SEO変化と企業優遇の構図
SEOの変化も見逃せない要素です。Googleは検索品質の向上を目指し、YMYL(お金や健康など重要なテーマ)に関しては「信頼性のある情報発信者=企業・専門家」を優遇する傾向にあります。
企業サイトは豊富な資金で記事を量産し、被リンクを得る戦略も強力です。一方で個人ブロガーは人的・金銭的リソースに限界があり、検索上位を取るのがますます困難に。
この不公平とも言える構図が、個人による副業ブログをますます「オワコン」と思わせる要因になっています。
まとめ
副業ブログが「オワコン」と言われる理由は単なるイメージではなく、環境の大きな変化に根差した現実です。しかし、正しい対策を講じれば突破口も存在します。次の章では、2025年以降の個人ブロガーが直面するリアルな壁について深掘りしていきます。
2025年以降における個人ブロガーの不利な立ち位置
企業サイトのドメインパワーとYMYL問題
副業ブログを始める人が直面する最大の壁のひとつが、企業サイトとの圧倒的な「ドメインパワー」の差です。特に健康・お金・法律など、いわゆるYMYL(Your Money or Your Life)領域では、Googleは個人よりも企業や公的機関の情報を優遇しています。


なぜなら、YMYLジャンルは人々の人生に直接影響を与える内容が多く、信頼性が最も重視されるからです。例えば、医療情報について個人が書いた記事と、病院が監修した記事が並んでいたら、後者をクリックしたくなるのが人間心理でしょう。
この構造的な壁により、個人ブロガーが本来の実力を発揮できずに、競争の土俵にすら立てないケースも少なくありません。
被リンク戦略・情報網の格差
SEOにおいて上位表示を狙うには「被リンク」が重要です。被リンクとは、他のWebサイトから自分のブログへリンクを張ってもらうことで、Googleは「このサイトは他からも評価されている」と判断します。
しかし、企業サイトは広報・取材・グループ企業などから大量にリンクを得られるのに対し、個人ブロガーは人脈も影響力も限られ、リンクを集めるのが非常に困難です。
また、取材費や調査リソースをかけられる企業と違い、個人は主に検索ベースの情報収集が中心。これにより、一次情報・権威性・情報鮮度といった面で後れを取るリスクも高くなります。
新規参入者が感じる難しさとは
こうした背景から、新規参入者の多くが「ブログってこんなに厳しかったの?」とギャップを感じて離脱してしまいます。
ブログ運営では「最初の3ヶ月〜半年は無収入が当たり前」と言われますが、現代ではそれ以上に心理的・構造的なハードルが多く、心が折れてしまう初心者も少なくありません。
特に「今から始めて本当に成果が出せるのか」という不安が先行し、書く前から諦めてしまうケースも見受けられます。
まとめ
2025年以降の副業ブログは、企業サイトとの力の差が広がり、YMYL領域では特に参入障壁が高まっています。しかし、この現実を正しく把握することで、自分が戦うべき土俵を見極めることが第一歩となります。
“昔のやり方”が通用しなくなった決定的な要因
旧来のSEO&アフィリエイト手法の限界
かつては「キーワードを詰め込めば上がる」「とにかく数をこなせば稼げる」と言われた時代もありました。しかし、Googleのアルゴリズムは年々進化し、今では単なる情報の寄せ集めでは上位表示は難しくなっています。
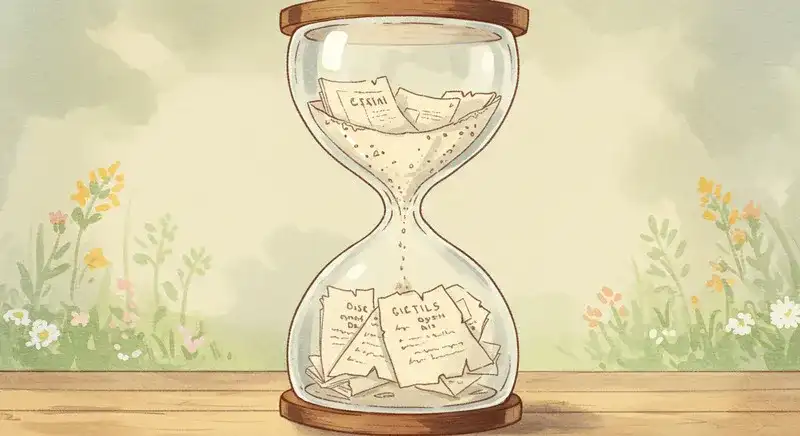
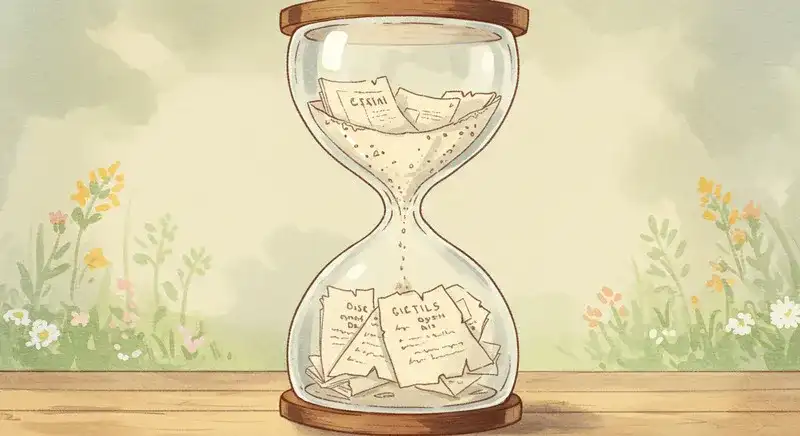
たとえば、10年前に通用したような“量産型テンプレ記事”や“自演リンク”といった手法は、現在ではスパムと見なされる可能性もあります。
さらに、アフィリエイトにおいても、「どの広告が儲かるか」だけで記事を作るスタイルは、読者にも見抜かれるようになり、成果が出にくくなっています。
ステマ規制による信用低下と収益影響
2023年10月に導入されたステマ(ステルスマーケティング)規制は、個人ブロガーにとっても大きな転換点でした。
これにより、アフィリエイト広告には「PR」や「広告」といった明示的な記載が義務化され、読者にとって“広告感”が強まってしまいます。
その結果、商品の良さを自然な流れで伝えることが難しくなり、成約率の低下にもつながっていると言われています。信頼性を高める工夫が求められる中、単なる商品紹介では稼げなくなっているのです。
Googleアップデートによる大変動
Googleは年間に数回、コアアップデートと呼ばれる大規模なアルゴリズム変更を行っています。これにより、過去に上位表示されていた記事が突然圏外になるケースもあります。
特に2023年には4度のアップデートが行われ、ジャンルによっては個人サイトが軒並み順位を落としました。
このような環境下で生き残るには、単に記事を書くだけでなく、「読者の検索意図」「信頼性」「網羅性」など、複合的な評価基準に応える必要があります。
まとめ
かつて有効だった手法は、今では通用しません。アルゴリズムの進化や規制の強化により、“書けば稼げる”時代は終わりました。これからは本質的な価値を提供できるコンテンツこそが生き残る時代です。
次章では「稼げないブログの特徴とAI時代の勝ちパターン」について深掘りしていきます。
稼げないと言われるブログでも戦うには?
稼げないブログの特徴と実例【AI×量産 vs 手動ライティング】
AI乱用による記事の質の低下と信頼の崩壊
近年、AIを活用した記事作成が急速に広まっています。特に副業ブロガーの間では「とにかく量を出せば稼げる」という旧来の考え方から、AIに任せて記事を量産するケースが増加しています。
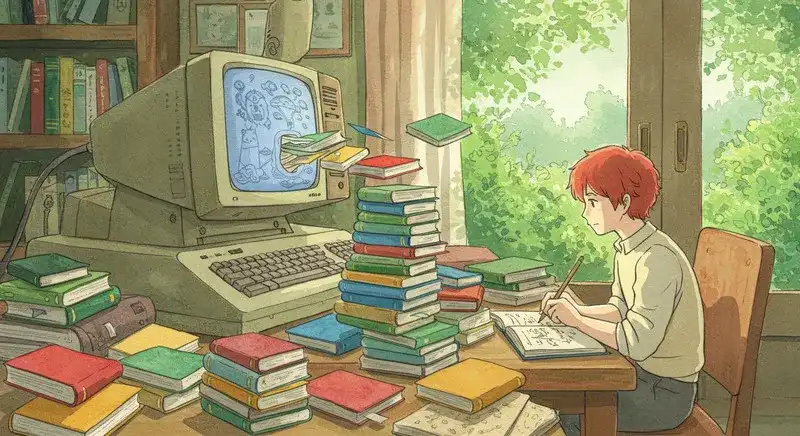
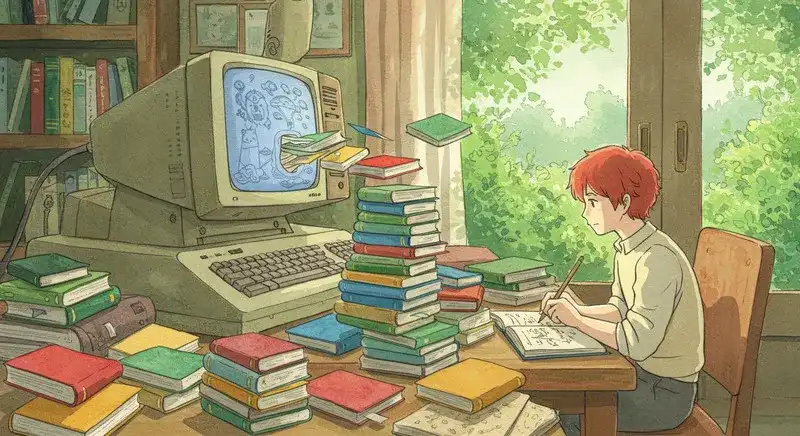
しかし、精度の低いプロンプトで生成された記事は内容が薄く、読者にとって有益な情報がほとんど含まれていないことが多いです。結果として滞在時間が短くなり、Googleの評価も下がってしまいます。
さらに、事実確認が不十分なまま公開された記事は、検索エンジンのみならず読者の信頼をも失います。稼ぐどころか「読む価値のないブログ」として見切られてしまうのです。
人間味がない記事が持つ致命的弱点
もう一つ見落とされがちなのが、AIが生成した文章に「人間らしさ」が欠けていることです。確かに情報を効率よく整理する能力には優れていますが、読者が求めているのは共感やリアリティです。
例えば「節約術」についての記事を読む際、実際に苦労しながら貯金に成功した人の体験談と、ツール的な手法だけを紹介した記事とでは、圧倒的に前者の方が読まれやすい傾向にあります。
読み手が「これ、自分にもできそう」と感じられるかどうかが、成約率やリピート率にも大きく影響します。人間味のないブログでは、それが極めて困難です。
継続せずに消えたブログの共通点とは
さらに多くのブログが収益化に失敗する大きな理由のひとつが「継続の断絶」です。最初の数ヶ月で結果が出ないと、更新をやめてしまう人は後を絶ちません。
稼げないブログには共通して、以下のような特徴があります。
- 投稿頻度が不安定で読者の信頼を得られない
- すぐに収益化を狙いすぎて読者への価値提供が薄い
- 自分の得意分野でないジャンルを選んでいる
AIに任せるにしても、戦略的に活用し、継続的に改善・更新する姿勢がなければ成果には結びつきません。
まとめ
稼げないブログには、AI依存による質の低下、人間味の欠如、継続性の欠如といった明確な原因があります。これらを避けることで、読者に信頼されるブログを構築することが可能です。
それでも副業ブログが機能する条件とは?
ニッチな専門領域での「体験」に価値がある
2025年現在、副業ブログが生き残るためには「体験のリアルさ」が重要な武器となっています。誰でもアクセスできる情報よりも、個人の一次情報のほうがGoogleにも読者にも評価されやすくなってきました。


例えば、発達障害の子どもを育てる家庭が、体験ベースで書いた教育グッズのレビューは、多くの親にとって貴重な情報です。これは企業が絶対に真似できないリアルなコンテンツになります。
自分が経験してきたことを、悩んでいる誰かの「答え」に変換できることこそ、個人ブログ最大の価値です。
SEO以外の導線(SNS・動画等)との連携
検索からの流入だけに頼る時代は終わりました。今はX(旧Twitter)やYouTube、InstagramなどのSNSを通じて、自分のブログに人を集める導線を複数持つことが必要です。
特にYouTubeでの発信は信頼性を高める効果があり、ブログとの相乗効果が期待できます。視聴者が「この人の意見なら信用できる」と感じたとき、ブログ記事の説得力も大きく増すのです。
このように、SEOとSNS、動画を組み合わせた“マルチ導線設計”こそが、これからのブログ成功パターンです。
継続と信頼性が築くマネタイズルート
どんなジャンルであれ、継続なくして成果は生まれません。記事数が増えるほど、検索流入も評価も安定しやすくなり、収益も発生しやすくなります。
また、信頼性の高い記事を積み上げていけば、広告主や提携先から直接依頼が来ることもあります。これはアフィリエイトとは別の収益ルートであり、安定性も高いのが特徴です。
たとえすぐに結果が出なくても、積み重ねることで確実に「資産型ブログ」へと育っていきます。
まとめ
副業ブログが機能するためには、体験ベースの情報発信・SNSとの連携・継続による信頼構築が不可欠です。これらを満たせば、個人でも十分に戦える土俵が整います。
個人ブログが通用する3つの戦略ゾーンとは?
体験×レビュー=一次情報戦略
Googleは近年、一次情報に高い価値を置いています。特に個人の実体験をもとにしたレビュー記事は、他では得られないオリジナリティと信頼性があります。


例えば、「実際に使ってみたレビュー」や「失敗談とその改善策」といった体験談は、読者の悩みに直接響きます。商品スペックを並べるだけの比較記事とは、説得力に明確な差が生まれます。
情報の鮮度や実感値を伴う体験コンテンツこそが、今のSEOで通用する情報の鍵です。
Googleが拾いにくい「超ロングテールKW」
競合がひしめくビッグキーワードでは、企業サイトが強すぎて個人は太刀打ちできません。しかし、検索数が少ない「超ロングテールキーワード」では話が変わります。
たとえば、「40代 子育て中 主婦 副業 時間がない」など、悩みをそのままキーワードにした検索語句には、意外と競合が少なく、個人が上位を取れるチャンスがあります。
検索ボリュームが少なくても、複数記事で積み上げていけば、月間1万PV以上を安定して狙えることも十分可能です。
属人性を活かした「ファン化ブログ」
最後に注目すべきは「属人性」、つまり「あなたにしか書けないコンテンツ」を発信することです。読者が記事を通じて筆者に親しみを感じ、ファン化すれば、商品紹介や有料サービスの成約率も高まります。
たとえば、ライフスタイル・育児・特定の疾患など、共感を生みやすいテーマで書き続けることで「この人のブログを読めば安心」と思ってもらえるようになります。
ファン化された読者は、Google検索よりも早くあなたのブログにアクセスしてくれるようになります。
まとめ
個人ブログが勝てる戦略ゾーンは、一次情報・ロングテールKW・属人性の3つです。これらを的確に狙うことで、大手企業にも負けない「個人ブランド型ブログ」が形成できます。
次章では「ブログ収益の現実と“月1万円の壁”の正体」について、より踏み込んで解説していきます。
これからのブログ副業を成功させるには
ブログ収益の現実と「月1万円の壁」の正体
収益発生までの平均期間とPVの目安
副業ブログを始める人にとって、最も気になるのが「いつ収益が発生するのか」という点でしょう。結論から言えば、平均して収益発生までには3〜6ヶ月、月1万円を超えるには1年以上かかるケースが一般的です。


なぜなら、Google検索での流入には「ドメインの評価期間」や「記事の蓄積」が必要だからです。さらに、PV(ページビュー)数に比例して収益が上がる構造上、最初の1000PVを超えるのにも苦労する初心者は多いものです。
例えば、実際に月1万円を超えているブロガーでも「最初の半年は0円だった」という声は珍しくありません。それだけ継続と改善が必要な領域だといえます。
1万円以上稼ぐ人の割合とその要因
2023年のデータによれば、ブログで月1万円以上稼げている人の割合は全体の約46%。つまり、約2人に1人は1万円の壁を超えている計算です。
この差を分ける要因は「継続」と「設計力」です。単に記事を書くのではなく、収益につながるテーマを選び、導線や広告配置まで意識して構築できている人は、やがて収益化に到達します。
一方で、好きなことだけを気ままに書くスタイルでは、よほどのSNS拡散がない限り収益に結びつきにくいのが現実です。
ブログ収益を下支えする広告の選び方
月1万円の壁を突破するには、掲載する広告の選び方も重要です。
成果報酬型(アフィリエイト)とクリック報酬型(Googleアドセンス)にはそれぞれ特徴があります。特に初心者には、クリック1回で数十円の収益が入るアドセンスの導入がハードルが低く、継続のモチベーションにもつながります。
一方、アフィリエイト広告は単価が高い反面、読者の購買行動まで設計しないと成果が出ません。紹介する商品やサービスが読者のニーズに合っているかどうか、しっかり見極めましょう。
次は「AIを使って効率的に記事を量産できる時代に、どこまで“人間らしさ”が必要なのか」について掘り下げていきます。
AIで効率化するなら、どこまで“人間の味”を加えるべきか
AI記事の活用例と限界
AIの進化により、記事の下書きや要約生成は以前より格段にスピードアップしました。例えば「ChatGPT」や「Notion AI」を活用すれば、構成作成からリード文まで一気に出力できます。
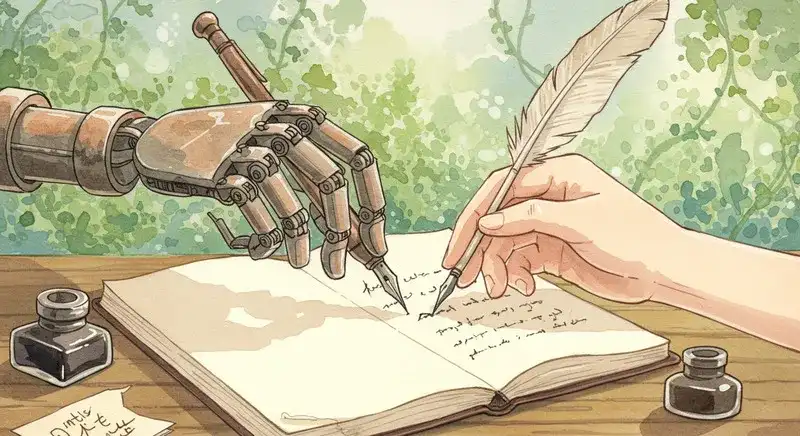
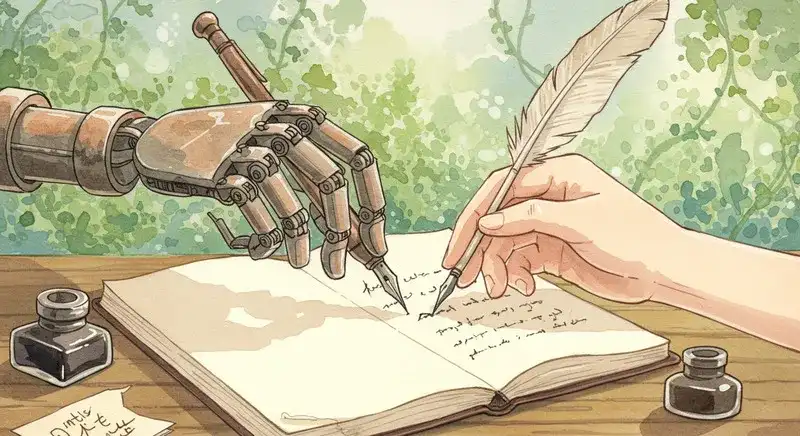
しかし、問題は「内容の深み」と「文体の均一さ」です。AIが生成する文章はロジカルですが、どこか無機質で読者の心に残らないという弱点があります。
AIを使って時短することは有効ですが、すべてを任せきりにすると、信頼性や独自性の欠如につながるリスクもあります。
人間の「実体験」「主観」の価値とは
ここで鍵になるのが、人間にしか書けない「体験談」や「主観的な感想」です。
「実際に試してよかった」「失敗したけれど学びがあった」など、リアルな感情が入ることで読者との距離がぐっと縮まります。読者は情報だけでなく、「この人の言うことなら信じられる」という安心感を求めているからです。
特に副業ブログでは、同じ悩みを抱えている読者が多いため、実体験ベースの発信は非常に有効です。
読者が共感・信頼する文体と構成
読者に読まれる記事には、共通点があります。それは「やさしく語りかけるような文体」と「論理的な構成」です。
難解な表現や専門用語の羅列は読者を遠ざけてしまいます。逆に、感情の起伏や問いかけを交えた構成は、読者の集中力を持続させます。
たとえば「あなたもこう感じたことはありませんか?」という一文があるだけで、共感度は大きく変わるのです。
次章では、そうした“人間らしい”ブログをさらに活かすために、SNSやYouTubeなどの他メディアとの併用について紹介していきます。
SNS・YouTubeとの併用が必須な理由
SEOリスクの回避と導線の分散
Googleのアルゴリズム変更は、個人ブログにとって死活問題です。上位表示されていた記事が突然圏外に飛ばされ、収益がゼロになることも珍しくありません。
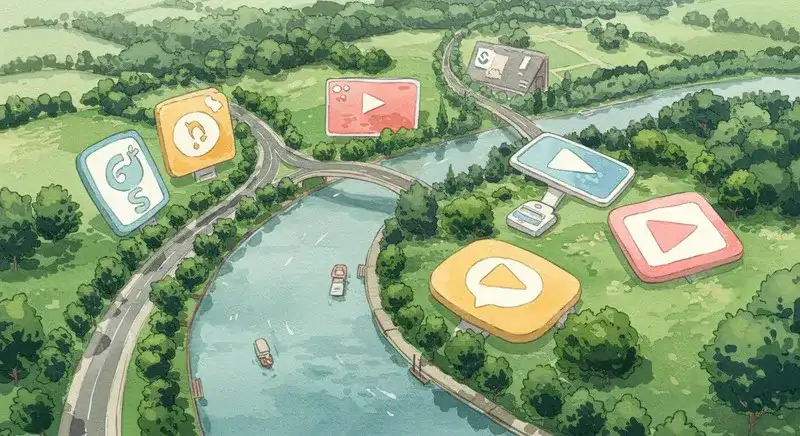
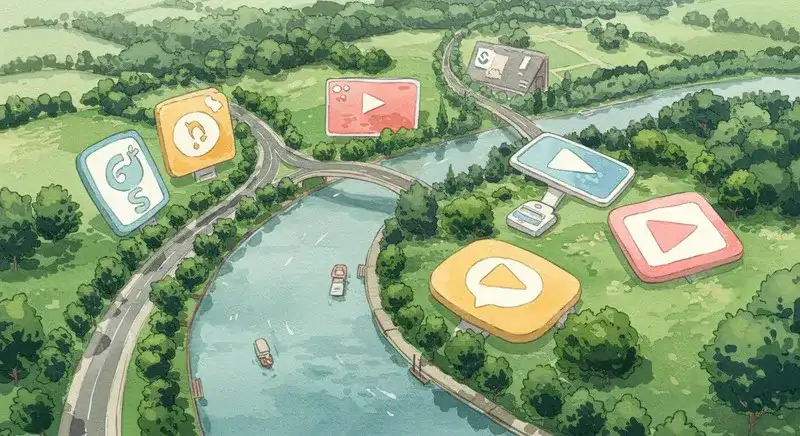
だからこそ、検索エンジンだけに依存するのは非常に危険です。Twitter(現X)やYouTube、InstagramなどのSNSと連携して複数の集客導線を持つことで、安定性が高まります。
導線の分散は、リスクヘッジだけでなく、ファン獲得にもつながります。
SNSからの濃いアクセスの活かし方
SNSの強みは「関係性を育てられる」点にあります。単に記事のURLを貼るのではなく、普段から共感を得られる発信をしておくことで、読者の信頼を獲得できます。
たとえば、日常の気づきや作業報告をポストすることで、「この人のブログ、読んでみたい」と思ってもらいやすくなります。
また、フォロワーが拡散してくれれば、SEO以上の爆発力を生むことも可能です。
マルチチャネル時代の副業戦略
現代の副業は、単一メディアで勝つ時代ではありません。ブログ、YouTube、SNS、音声配信など、複数のメディアを戦略的に使い分ける必要があります。
たとえば、YouTubeでファンを獲得し、ブログで深掘り解説を提供する。Xで拡散し、公式LINEでコミュニケーションを取る。こうした連携によって、個人でも「小さなメディア帝国」が築けるのです。
続く章では、ブログ運営がもたらすスキルをいかに他分野へ活かすか、その具体的な戦略を見ていきましょう。
次の章:スキル展開を前提にしたブログ設計のすすめ に続きます。
実践ステップとマインドセットの再確認
- テーマ選定の“3条件”とは?【需要・得意・収益性】
- 収益化までに必要な期間とマインドセット
- 今こそ「自分の実体験」を武器にする理由
- 本気でブログで稼ぐなら、まず〇〇を整えよう(CTA)
- 副業ブログがオワコンと言われる時代の戦い方まとめ
テーマ選定の“3条件”とは?【需要・得意・収益性】
市場ニーズを把握するリサーチ方法
ブログで成果を出すには、需要のあるテーマを選ぶことが最優先です。つまり「読まれるテーマ」でなければ、どんなに良い記事を書いても見られることはありません。


Googleキーワードプランナーやラッコキーワード、Ubersuggestなどのツールを活用し、検索ボリュームを確認しましょう。また、Yahoo!知恵袋やX(旧Twitter)のトレンドなども、リアルな悩みやニーズの宝庫です。
読者の「知りたい」に応えるテーマを選ぶことが、最初の突破口となります。
自分の強み・経験をテーマに活かす
他人と差別化するためには、「自分しか書けない」視点が必要です。その核になるのが、これまでの経験や得意分野です。
たとえば、「営業経験10年のノウハウ」や「地方移住してよかったこと」など、自分だけの体験は強力な武器になります。何気ない失敗談や気づきでも、読者にとっては貴重な一次情報です。
「詳しい人」より「経験した人」から情報を得たいという読者心理に応えられます。
アフィリ報酬単価とのバランス感覚
需要と得意分野がかみ合っていても、収益化しにくいテーマでは稼ぎづらいのが実情です。そこで意識したいのが「単価の高さ」と「成約率の見込み」です。
美容や金融、転職、通信などは単価が高い一方で、競合も強力です。逆に、ニッチな趣味ジャンルは成約率は高くても単価が低い傾向があります。
「PVが少なくても収益が出る構造」を作るには、アフィリエイト案件の報酬額と訴求のしやすさをよく見極めることが重要です。
続いては、テーマを選んだあとに待ち構える「収益化までの期間と心構え」についてお話しします。
収益化までに必要な期間とマインドセット
ブログ収益化は最低でも半年〜1年
ブログは、スタート直後から稼げるビジネスではありません。一般的には、収益が安定し始めるのに6ヶ月〜1年かかるとされています。


これは、検索エンジンがサイトを評価するまでに時間がかかるためです。また、記事の質と量が蓄積されることで、ようやく収益の土台が整うのです。
この期間は、収益が出ないことへの焦りや不安と向き合うフェーズでもあります。
「諦めない力」よりも「続ける設計」が重要
モチベーションに頼った継続は限界があります。大切なのは、作業を「習慣化」し、「仕組み化」することです。
たとえば、「毎朝30分だけ執筆する」「日曜に3本まとめ書きする」といったルールを自分に課すことで、挫折リスクを下げられます。
また、執筆の工程をテンプレ化したり、AIを補助に使ったりすることで、継続のハードルを下げる工夫も重要です。
失敗経験から学んだ成功パターン共有
多くの成功ブロガーも、最初は失敗を繰り返しています。検索ニーズを無視した記事を書いてしまったり、アフィリリンクだけを貼って読者離れを招いたり——そのたびに試行錯誤してきたのです。
「何が失敗だったのか」「どこで改善できたのか」を振り返り、他人の失敗談も積極的に学ぶことで、自分のブログ戦略にも応用が効くようになります。
次の章では、これからの時代に特に強みになる「自分の実体験」にフォーカスを当てて解説します。
今こそ「自分の実体験」を武器にする理由
AI時代だからこそ体験談が差別化になる
生成AIが普及し、誰でもそれなりの文章を量産できる時代になりました。その中で人間の価値を示せる最大のポイントは「実体験」です。


AIが語れない「体験から得た感情」や「リアルな気づき」は、読み手の心を動かします。ブログで成功している人の多くが「等身大の体験談」を武器にしています。
差別化が難しい今だからこそ、「あなた自身のストーリー」が求められているのです。
読者の共感を生むストーリー構築
ただ体験を書くだけでは読まれません。共感を呼ぶためには、「読者が自分ごととして捉えられる構成」が必要です。
例えば、「悩み → 試行錯誤 → 解決 → 学び」という流れをベースにすれば、読者も自身の課題と重ねやすくなります。
また、失敗談を正直に語ることは、信頼感の構築にもつながります。人は完璧な成功談よりも「乗り越えた過程」に魅力を感じるものです。
経験×情報=信頼性の高いコンテンツへ
体験と事実情報を掛け合わせることで、コンテンツは一気に信頼性を増します。
たとえば、「自分はこうして副業ブログで月1万円を超えた」という話に、「この手法で成功した人は全体の46%」といったデータを添えれば、説得力が倍増します。
読者にとって信頼できる情報源になるためにも、「自分の経験+根拠ある情報」を意識しましょう。
最後に、これから本気でブログ収益化を目指す方に向けて、最初に整えるべき土台についてご紹介します。
本気でブログで稼ぐなら、まず〇〇を整えよう(CTA)
WordPress+独自ドメインが基本土台
本格的にブログ収益化を目指すなら、無料ブログでは限界があります。理由は「広告制限」「運営側の都合で削除されるリスク」があるためです。


収益を最大化するには、WordPressを使い、独自ドメインでブログを運営することが必須です。初期費用こそかかりますが、自由度と信頼性は圧倒的に違います。
初期設定でやるべきこと(SSL・テーマなど)
ブログ開設直後は、SEOや表示速度に関わる基本設定を忘れずに行いましょう。
- SSL化(https化)でセキュリティと信頼性を強化
- SEOに強いテーマを選定(CocoonやSWELLなど)
- プラグインで機能拡張(SEO、キャッシュ、高速化)
こうした設定は、後回しにすると後々の手間になるため、最初にしっかり整えておくことが重要です。
読者導線と集客戦略の仕組み化が鍵
「記事をただ書くだけ」ではなく、「どうやって読者を呼び込み、どの導線で収益化するか」をあらかじめ設計しておく必要があります。
例えば、
- SEOで集客 → アフィリエイト記事に誘導
- SNSからの流入 → メルマガ登録へ
- YouTubeで認知拡大 → ブログで詳細解説
このように、集客から収益化までの導線を可視化することで、戦略的にブログを伸ばせます。
次の行動を明確にし、早めに仕組み化へ着手することが、ブログで稼ぐ土台づくりの第一歩となるでしょう。
副業ブログがオワコンと言われる時代の戦い方まとめ


- 副業ブログは収益化までに時間がかかり離脱者が多い
- 検索上位は企業サイトに占拠されており個人には厳しい
- SEO難化により質と信頼性が重視される傾向が強まった
- テキスト離れと動画・SNSの台頭がブログに逆風を与えている
- YMYL分野ではGoogleが企業や専門機関を優遇している
- 被リンク獲得の差が個人と企業の大きな壁になっている
- 新規参入者はブログの厳しさにギャップを感じやすい
- 旧来の量産・テンプレ手法は通用しなくなっている
- ステマ規制によりアフィリエイトの成約率が下がりやすい
- AIによる記事乱用が読者の信頼を損ねるリスクを伴う
- 体験に基づく記事が差別化と信頼構築の鍵になる
- ロングテールキーワードの攻略が個人の突破口になる
- 属人性を活かせばブログはファン獲得の場として機能する
- 収益化までの期間は長く継続する設計が不可欠
- SNSやYouTubeとの併用で集客と信頼性を補完できる
- テーマ選定には需要・得意・収益性の3条件が必須
- WordPress+独自ドメインで収益ブログの土台を整える
–




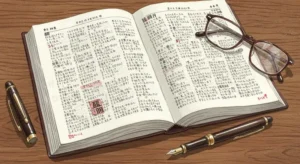
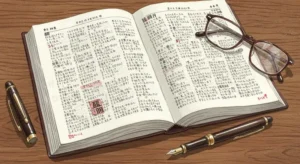






関連リンク
総務省統計局「家計調査」
副業ブログの収益性や家計への影響を考えるうえで、日本の一般家庭の収入・支出傾向を把握することは重要です。総務省が提供する「家計調査」は、月ごとの収支データをもとに、現実的な収益目標を立てる際に役立ちます。
http://www.stat.go.jp/data/kakei/index.htm
アフィリエイトマーケティング協会「アフィリエイト・プログラムに関する意識調査2023」
ブログ副業での収益源の1つであるアフィリエイトの最新動向を知るために有効な資料です。報酬発生の傾向や、稼いでいる人の特徴、業界全体の変化などが詳しくまとめられています。
https://affiliate-marketing.jp/release/202306.pdf
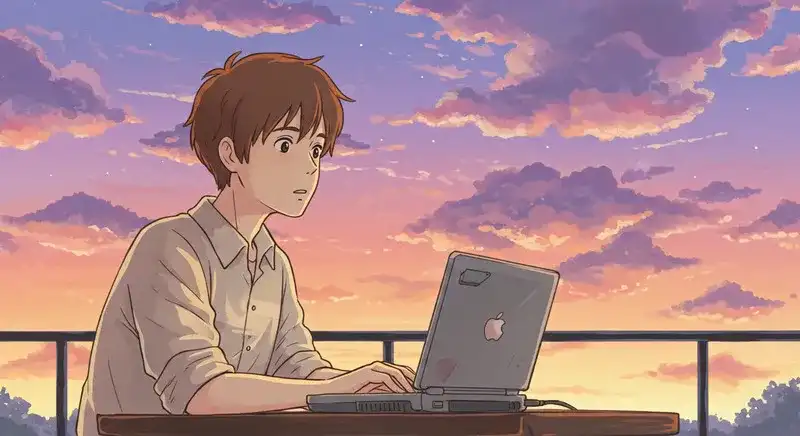
コメント