退職の連絡を、紙でもメールでもなく「LINE」で済ませる若者が増えている──。
2025年4月、あるアルバイト従業員がLINEで退職届を送った事例がSNS上で大きな注目を集めました。
「非常識だ」「いや、今の時代ならアリ」と意見は真っ二つ。
世代間の“常識”をめぐる価値観の違いが浮き彫りになっています。
Z世代をめぐる“働き方のリアル”に迫る
Z世代の常識が新しすぎてビビってる。
— シモミシュラン (@shimomichelin) April 13, 2025
Z世代がいつからか知らんけどとりあえず
10代を2度と雇うことはない😂
アホらしすぎて返す言葉なかったから
お疲れ様でした、しか返されへんかったわ。笑#退職届という名のライン pic.twitter.com/wwqpltpRTO
LINEで退職届──常識を揺るがす出来事の概要
2025年4月、ある5ちゃんねるの投稿がSNS上で大きな波紋を呼びました。
投稿者が晒したのは、アルバイトの若者が送ってきたという「LINEによる退職届」。
このたび、一身上の都合により退職したく思います。 お疲れ様でした。2週間、大変お世話になりました。
という簡潔ながら丁寧な文面に加え、給与の振込方法を尋ねるやり取りも含まれていました。
文面自体は特に問題なさそうですが、注目を集めた理由はその“手段”にあります。
「LINEで退職って非常識?」「それとも、もう普通のこと?」
SNSでは賛否が飛び交い、「時代が変わった」と感じた人も多かったようです。
紙か?メールか?LINEか? 現代の“適切な退職の伝え方”とは何なのでしょうか。
労働基準法から見た「退職の伝え方」
まず確認したいのが、退職の申し出はどのような形式なら有効とされるのか、という点です。
実は日本の労働法では、退職届に「紙」「対面」「押印」などの形式的な縛りはなく、意思が明確に伝われば原則として有効とされています(民法627条)。
つまり、メールでも、LINEでも、文面に辞意が記されていれば基本的には成立します。
厚生労働省のガイドラインでも、この点は明示されています。ただし、会社の就業規則で紙提出が定められている場合、そのルールが優先される可能性もあります。
とはいえ、法的な正当性よりも論争を呼ぶのは「常識」のほう。では、その“常識”とは誰の感覚によるものなのでしょうか?
–
まだこっちの方が気持ちはこもってると感じてしまいました。 pic.twitter.com/Cjys3Azpt2
— 毛王 (@kireina_keoh) April 14, 2025
–
世代間ギャップが炙り出す「常識」の正体
SNSの反応で顕著だったのは、世代によって「LINE退職」への受け止め方が大きく分かれていた点です。
40代以上のユーザーは、「けじめがない」「礼儀がない」といった否定的な意見が目立ちました。
一方で20代前後のZ世代は、「むしろLINEで伝えるだけ偉い」「バックれより100倍マシ」と肯定的。
この構図は他にも見られます。
- SNSでの連絡を仕事に使うことへの違和感
- 絵文字やスタンプが“ふさわしいか”という議論
- 電話 vs メール vs チャット文化の壁
「常識」とは、実は絶対的な基準ではなく、各世代が育ってきた環境と文化の中で形づくられた“感覚”に過ぎません。
変わりゆく常識にどう適応するか。 次は、現場レベルでの課題に注目してみましょう。
実際の職場ではどうなのか──現場のリアルとその温度差
法律上はLINEでも問題ない場合があるとはいえ、現場ではさまざまな摩擦が生じます。
例えば、LINEは「通知が届かない」「文面が曖昧」「送信時間が夜中」など、トラブルの火種にもなりやすいツールです。
今回の件でも、退職者が「給与の振込先をまだ伝えていない」ことに疑問の声が上がりました。
本来、雇用時に振込先は確認すべきであり、2週間働かせて未確認だったのは企業側の落ち度と見る声もあります。
さらに、「退職日当日にいきなり連絡」だったとすれば、民法上の“14日前の予告義務”にも触れる可能性が出てきます。
つまり、形式だけでなく「タイミング」や「伝え方の中身」も重要だということです。
では、Z世代はなぜこうした手段を選ぶのでしょうか。
デジタルネイティブ世代の“当たり前”とは?
Z世代をはじめとする若者は、生まれたときからスマホとSNSに囲まれて育っています。
LINEは彼らにとって「親しい友達」と同じ感覚で使えるツール。
就活の面接連絡、シフト調整、学校の連絡網さえもLINEで行われることは珍しくありません。
一方で、上司世代にとってLINEは「プライベートな空間」。
そこに仕事の話を持ち込まれることに強い違和感を覚えるのも無理はありません。
では、そのギャップをどう埋めればよいのでしょうか。
答えは「ルールと理解の両立」にあります。
共通ルールと相互理解が求められる時代へ
LINEでの退職がアリかナシかではなく、「どう伝えるか」「どう受け取るか」の共通ルールが重要になってきます。
たとえば、LINEを業務連絡に使う職場なら、
- 退職の申し出は最低でも◯日前に
- 既読確認と返信の義務
- 書面のフォローアップも推奨
など、あらかじめ明文化しておくことが有効です。
また、Z世代側も「常識が通じない上司」と切り捨てるのではなく、相手の立場を想像した対応を意識することが必要です。
その歩み寄りがなければ、今後も同じ摩擦は繰り返されていくでしょう。
次は、企業側の課題にも目を向けてみます。
「退職LINE」が企業文化に与えるインパクト
このような事例がSNSで拡散されると、企業にとっては想像以上のダメージを受けることもあります。
近年では「退職代行を使われた」「労働環境を晒された」ことでブラック認定され、採用に悪影響が出る企業も増えています。
逆に、「LINE退職も受け入れる柔軟な社風」として評価されるケースも。
つまり、重要なのは「退職された手段」ではなく、「その背景にある企業の体制」が問われているのです。
Z世代は、単に辞めやすい手段を選んでいるのではありません。
“納得できない労働環境”から最もストレスの少ない方法で抜け出そうとしているだけです。
それを防ぐには、働きやすい職場を作るしかありません。
まとめ:時代の変化にどう向き合うか
LINEで退職の意思を伝える──この行動を非常識だと切り捨てるのは簡単です。
しかし、その背景には、
- 法律と現場感覚のズレ
- 世代間の価値観の断絶
- 柔軟性を欠いた企業体制
といった複雑な構造が潜んでいます。
私たちがすべきなのは、「非常識」という言葉で片づけることではなく、何がズレていたのかを見極めることです。
時代は確実に変わっています。
その変化に、私たちはどう向き合うべきなのでしょうか。

「退職届は紙で」と言われて、紙パックのジュースに書いて出した子がいたらしいです。未来、強すぎる。
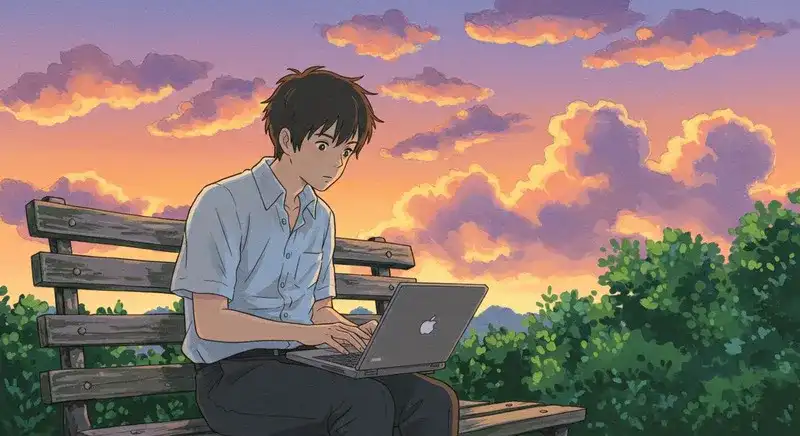
コメント