
メモを取っているのになかなか仕事が覚えられない



メモしてもどこに書いたか わからなくなっちゃって、探すのに時間がかかっちゃう



早く仕事をしないといけないからメモを見ている時間なんてないです。でもミスが多くて・・



上手なメモの取り方やまとめ方があれば知りたい!
そんな風にお悩みではありませんか?
メモをとれと言われてるからメモを取ってるけど、いまいちメモをとる必要性を感じない。
メモを取ったけど、いざ必要になったらどこに書いたのかが、みつからなくて結局見ないでやってしまう!
なんてこと、ありがちです。
私もメモの取り方や活用方法でいろいろ悩んだことがあり、考え抜いた末に「自分的にはかなり満足できる方法」を取ることができたので、その方法を書いていきます。



よろしければ、ぜひ最後まで御覧ください。
手順を覚えるのも結構たいへん!だからメモしましょう


仕事の手順をなかなか覚えられない、って人も多いですよね?
私も、要領が悪い方で、なかなか仕事を覚えられずに悩むことが多かったです。
でも、覚えられないんだったらメモを取っておいて、それを見ながらやればいいんです。
いくつかのコツさえ覚えてしまえば、圧倒的に早くミスなく仕事をすることが可能です。だって、メモをみながら、そのとおりにやればいいだけなんですから。
私が「仕事が覚えられない」「メモのまとめ方で困ってる」といった、そんなお悩みを解決することができたのが「50音インデックス式」でメモを整理しておく方法でした。
なぜメモを取るのか?メモを取って上手にまとめるメリット


メモを取るっていうのは、仕事の基本として新人さんだと特によく聞くことだと思います。
メモをとるのはたくさんのメリットがあります。
- あとで仕事の作業を確認できる
- メモを見れば、仕事の手順を思い出したり考えたりする必要がないので早く作業できる
- 「あっ、アレを忘れてた!」が防げるのでミスを減らせる
- 状況を整理して順序だてや優先順位をつけやすくできる
- 改善点や反省点をみつけるヒントにできる
ざっとあげると、こんな感じですね。
あとで仕事の作業を確認できる


メモしておくことで、一度教えてもらえば、次からは一人で間違いなく確実に仕事の作業ができます。
人の記憶とは曖昧ですから、その瞬間は覚えておけると思っても少し時間が経てば忘れてしまうことが多いです。
「こんな簡単な作業、メモするまでもないよ!」と思っていたのに、あとでやってみようとすると忘れてしまって「どうやったんだっけ?」ってこと、多いのではありませんか?
あとでメモを確認すれば、そのメモをした時の記憶が蘇ります。
手順をしっかりメモしておけば、一ヶ月後でも半年後でも同じ精度の仕事を再現できるんです。
メモを見れば、仕事の手順を思い出したり考えたりする必要がないので早く作業できる
メモに手順を順番に書いておけば、そのとおりにやればいいんですからノータイムで仕事にすぐ取りかかれます。
「えーっと、どうやるんだっけ?」なんて思い出す必要さえないです。
「あっ、アレを忘れてた!」が防げるのでミスを減らせる


メモを取らないのに仕事ができる人っていませんか?
ああいう人を見るたびに落ち込むことがありました。
でも、そういう人でも決まった仕事の順番を決めていて、その順番で仕事をしつつ思い出しながら仕事をしていることが多いんです。
そういう人に仕事のことを聞きに行くと、実際に仕事をしないで思い出しているので「途中の手順がひとつ抜けていたりする」といったことがあります。
教えてもらいにいって文句を言うわけにもいきませんよね?だって、文句など言おうものなら、そんな人に聞かれても、次からは教えたくないと思うでしょう。
だから、自分でメモをしておくことが大事です。
状況を整理して順序だてや優先順位をつけやすくできる
メモを取って記録しておけば、スケジュール管理などにもメリットがあります。
必要なことがメモしてあれば、それを見ればあとでいくらでも確認できるからです。
日程的やスケジュールは、それ専用のメモを用意してそこに順番に書いていきます。
そして、終わったら横線を引いていくだけでも何が残っているのか、残っているものにどれから取り組めばいいかがわかります。
箇条書きにするだけの超アバウトなメモ術でも、メモしないより遥かに生産性はあがるというものです。
改善点や反省点をみつけるヒントにできる
同じ仕事の作業を何度かしていると、「あれ、この作業って、こういう風にやってみたらどうだろう?」と思いつくことがあります。
そういったアイデアを試してみて、結果はどうだったかというのを簡単にメモしておけば改善案や楽に仕事をできるアイデアにつなげやすいです。
やってみたけどダメだった、やってみたらこの方が楽で早いかもしれない、というようなことでも、記録があればそれはすでに試してだめだったということがわかります。
あとになって、他によさそうな手順を思いついたのを試したり、問題が出たから元に戻すというのも記録として残ります。
試行錯誤の結果がデータとして残るので ノウハウが蓄積できるんです。
メモを取ることのデメリットや気をつけたいこと
ここまでメモを取ることのメリットを解説してみましたが、逆にメモをとっても活かせないといったデメリットもいくつか存在します。
- メモをとるのが面倒だし、時間がかかる
- 書いたメモが必要なときにすぐ出て来なかったり探すのに時間がかかって結局いかせない
こういった点を解決する必要が出てきます。
まず、メモを用意して文字を書いていきますから、当然時間がかかります。
そして、いざあとになって「○○のメモを確認したい」と思っても、それがなかなか出てこなかったりするんです。
数日前のことであれば、数ページを逆にたどっていけば みつかります。
ですが、半年以上前にメモしたものを確認するとどうなるでしょうか。
メモしたこと内容がなかなかみつからない、どこに書いたかわからない!ってことになりがちなんです。
これが、普通にメモしていく時の最大の問題でした。
では、どうしたらいいかを書いていきます。
メモは取り出しやすいものを選んで、箇条書きで簡潔に書いていく
メモは携帯しやすいサイズのものを選んで、必要になったらサッと取り出せるものを用意したいです。
必要な時にサッと取り出して、ぱぱっと書いてさっとしまう。
そんなイメージがベストですね。
場所の制限がないならA4のコピーをバインダーで止めて書いていくとかでもいいですし、携帯したいのであればA6サイズのメモ帳などにさっとメモをする感じです。
あとで見返したり、確認する可能性が高いメモは50音順にならべてまとめておく
あとになってメモを見返す時に、直近であれば書いた日付などであたりをつけてさかのぼって探せばOKですよね。
では、すぐにはつかわないけどあとになって必要になりそうなものはどうしたらいいでしょうか。
そういった場合は、50音順にまとめる専用のメモを用意しておけば、あとで探す時に便利になります。
あ・い・う・え・お~わ・お・んまで、順番にまとめてファイルしておく感じです。
面倒ですが、必要なところだけ書きうつすとか、コピーして貼り付けるようにすれば整理の時間は最小限で済むと思います。
特に見出しとかつけておかなくても、50音順にきちんと並んでさえいれば、それなりに早く探せますが、もちろん「見出しインデックス」とかつけてもOKです。
ちょっとお値段はしますけども、ルーズリーフバインダーなら大学ノートのサイズから小振りな携帯できるサイズまでありますし、必要に応じて並び替えたりできるので、使い勝手が良くておすすめです。
メモを活かすためにやっておきたいルール
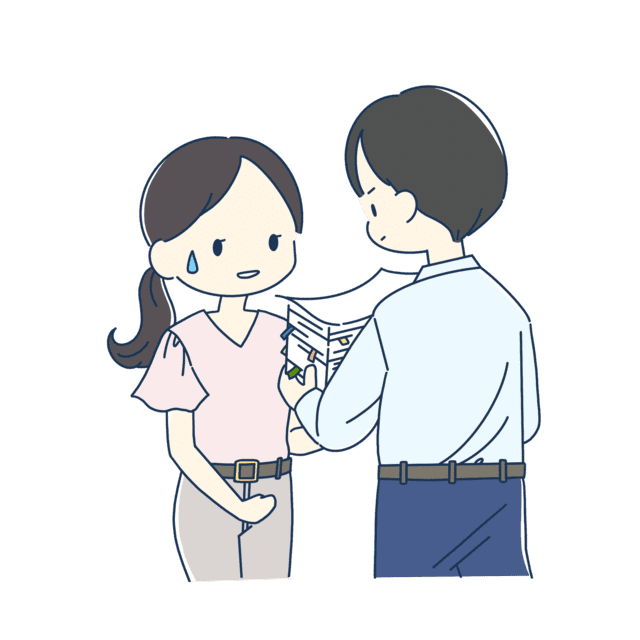
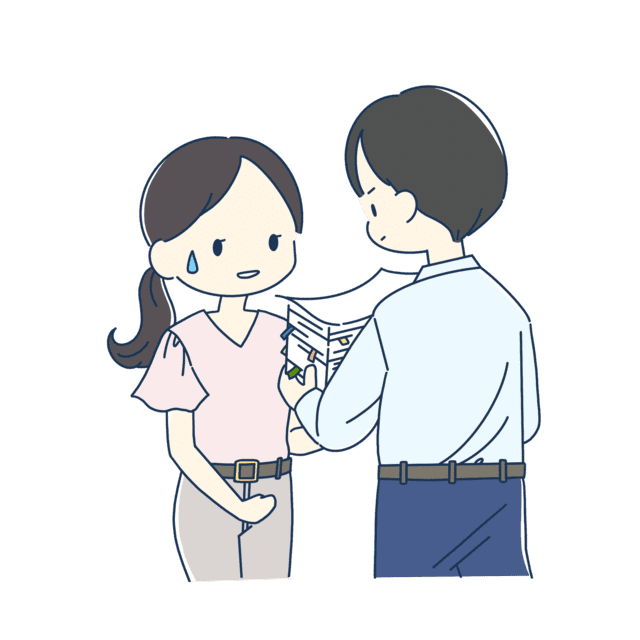
メモを活かすために守ってほしいルールが存在します。
- 文字はあせらずしっかり書く
- メモやノートはあまりふやしすぎない
といったことに注意してほしいです。
文字はあせらずしっかり書く
これは私がやった失敗なんですが、焦ってメモを取ったらあとになって見返した時に、「これはなんて書いてあるんだろう」となってしまって、メモを活かせなかったことがあります。
時間がないとメモを取るのにも時間がいるので気が焦ってしまうものですが、あとになって読めないと、逆に効率が悪くなってしまいます。
逆にメモはほんとうに最低限にするとか、いっそメモをとらずに覚えておいて、時間がとれた時にさっとメモをするほうが効率的なこともありますね。
メモやノートはあまりふやしすぎない
それは、メモをとる媒体は「できれば一元管理」でひとつだけ、多くても3つまでにするなど、「できるだけ少なくする」ことです。
メモを取る際に仕事とプライベートと趣味とレシピとパソコンと・・なんて感じでいくつにもわけてしまうと、どこに書いたかがわからなくなってしまいます。
探せばいつかは出てきますけど、探すのが面倒だったり時間がかかってしまったのでは本末転倒です。
いくつにするかは、ケースバイケースだと思いますが、仕事とプライベートで分けて2つ、多くても3つくらいがベストでは無いかと思います。
私の場合、基本的にメモはスマホアプリのEvernoteに記録するけど、実際に細かい手順は紙のメモに書いてファイリングしておいて、実際の作業はそれをみながら行うという方法で2つにしていました。
紙のメモは仕事の細かい手順だけなので、基本的にはEvernoteをみればすべて解決といった感じです。
こんな感じで、メモは少ない方がどのメモに書いたかわからないなんてのが防げるのでおすすめです。
メモ術関連のおすすめ書籍
メモに関係する書籍はけっこう出ていますので、興味がある方は読んでみるのをおすすめします。
中古だとかなり安く買えることも多いので、目を通してみてはいかがでしょうか。
50音インデックス式でメモをする場合に必要なもの
ここからは、わたしがやっていたメモ方法はこんな感じでしたというのを書いてみます。
よければ参考にしてみてください。
50音でメモを取るのに準備したもの
- A4のダイソーのレバー式バインダー
- A4(コピー)用紙
- コクヨ タックインデックスシール 紙ラベル
これだけです。全部ダイソーで揃えれば330円ぽっきり。
A4コピー用紙はまとめて買えば更にお得ですが、なければルーズリーフ用の用紙でも可です。でも少々お高いかも。
50音インデックス式メモ術【メモの取り方のポイント】
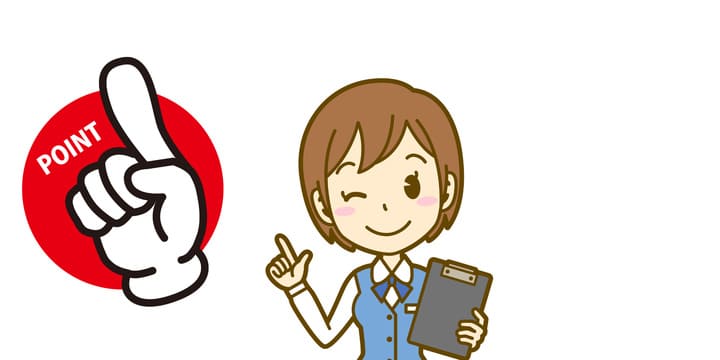
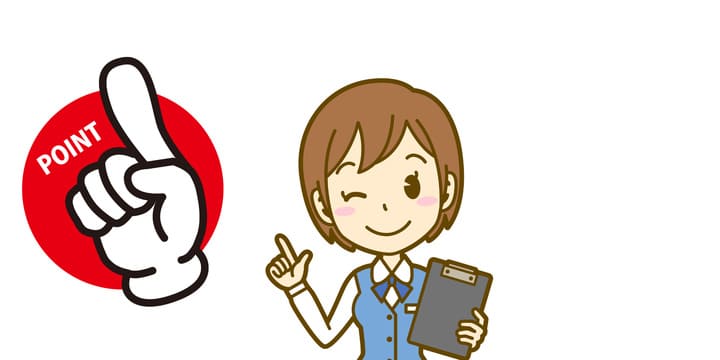
次はメモの取り方について解説していきます。
- 書く項目・内容を統一してあとでそのメモを探しやすいように書く
- 1ページ(1枚)にひとつの仕事を書く
- 忘れてしまう前提で全部の手順を簡潔に書く
- 基本は単色で。必要な時は青・赤も使って書く
書く項目・内容を統一してあとでそのメモを探しやすいように書く
例えばですが、「いろは社」の「コスメ用ケースの検査」という仕事だったとします。
A4用紙の左上に「いろは社」、上の中央に「コスメ用ケースの検査」、右上に日付を書きます。
あとは、その仕事の手順を順番に書いていくだけです。
その時に注意するのは、できるだけ「全部の要素を簡潔に書く」ということです。
・ロッカーから検査用品AとBを持ってくる
・Aを左、Bを右で(机に)置く。
・コスメケースを白い方を左にして、検査用品AにのせてBでチェックをする
こんな感じで、箇条書きで簡単にできるだけ全部を書いていきます。
最初から最後まで全部書いても5分あれば書ききるくらいのが理想です。
文章で時間がかかるなら、絵でラフに書いてもいいです。
あとでわかればいいので、キレイな字で書く必要はないです。
1ページ(1枚)にひとつの仕事を書く
A4用紙一枚に、ひとつの仕事だけ書きます。
スペースがあるからと一枚の用紙に2つ、3つを書いていってしまうと後で探しにくいので、基本一枚にひとつを書きます。
忘れてしまう前提で全部の手順を簡潔に書く
上の例の「ロッカーから検査用品AとBを持ってくる」を「検査用品AとBを持ってくる」と書くと、あとになって
「あれ? 検査用品Aはどこにあるんだっけ?」
という風になりがちです。
ラフでいいので、できるだけ全部の要素を書く理由がこれになります。
基本は単色で。必要な時は青・赤も使って書く
カラフルに書くのを推奨するメモ術もありますが、基本的に一色でいいと思います。
あとになって、見づらくなってきた時に補足で書き足すときに青を使ったり、
忘れがちだったり、重要なポイントを赤で追記するなど、個人的には3色くらいで十分だと思います。
50音でインデックス式メモしたメモのまとめ方
では、ここからはまとめ方です。
A4コピー用紙にコクヨ タックインデックスシールを貼って10枚のインデックスを作る
作ったインデックスに「あ」~「わ」まで順に書く。
「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「ら」「わ」
という風に、書いたら少しずつ下にずらしながらシールを貼って見出しインデックスを10枚作ります。
書いたメモを50音のインデックスに従って挟(はさ)んでバインダーで束ねていく


ここからはメモをまとめていきます。といってもインデックスでならべてバインダーに挟むだけです。
「いろは社」の「○○」という仕事のメモなら「あ」のインデックスの下に。
「ほへと社」の「△△」という仕事のメモは「は」のところという具合です。
この時に、すでに前のメモがあったら50音順に並べて挟んでいきます。
ほへと社のメモを挟む時に、「ひりゅう社」「ふがく社」のメモがあったら、その下に「ほへと社」のメモを挟むという具合です。
あとになって探す時には、「ほへと社」だから「は」のインデックスのメモを上から順番に見て探すだけです。
50音インデックス式メモ術【メモの整理や見返し方で悩む方向けのおすすめメモの取り方】まとめ


以上がこのメモ術のやり方でした。
これはオフィスワークの人よりも、現場で実際に作業する人に向いているかもしれません。
このメモ方法のメリットとデメリットは次のようになります。
このメモ術のメリット
- A4コピー用紙なのでコストが安く、どこででも手に入る
- あとで必要になった時に探しやすい
- 必要になったらA4用紙一枚だけ取り出して、そのメモを見ながら作業をすればいい
このメモ術のデメリット
- A4ノート一冊なのでポケットには入らない
- 挟む作業がちょっと面倒
A4バインダー1冊の置き場所さえ確保できれば大きなメリットがあるメモ術だと思っています。
携帯性を重視するなら、A4を半分に切ったB5の大きさの用紙にすれば持ち歩きに便利になります。
ただ、一枚にまとめるのがたいへんになってしまうのが欠点ですね。
A4用紙1枚に仕事の内容をまとめるというのは、あのトヨタでも実際に行っているメモ術です。
それを「50音順で並べて、あとで探しやすいように検索性を高めよう」っていう考え方です。
このメモ術は、わたしと友人とで「ノートの取り方」をテーマにした書籍を何冊も読んで試行錯誤した末に、これが一番いいかもという結論になったものです。
このメモ術で忘れっぽい私の仕事のミスは大きく減りましたし、作業も早くできましたので、興味がありましたら、ぜひ試してみてください。
少しでも参考にしていただければ嬉しく思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
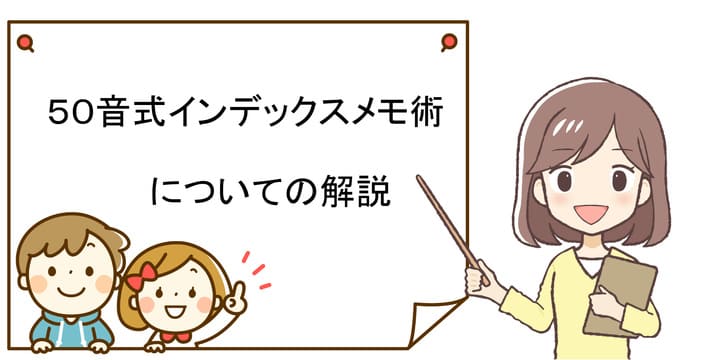


コメント