
恵方巻って子供の頃は聞いたこともなかったけど、いつからあるの?



食べる時に向く方角って毎年違うのは、なぜなの?



2022年の方角は北北西です。
恵方巻きは、江戸時代から明治時代の頃に大阪の花街で節分をお祝いしたり、商売繁盛を祈って食べたのがルーツといわれています。
全国で広く食べられるようになったのは1989年に、とあるコンビニエンスチェーンが広島県で太巻きを売りだしたのが始まりで、そこから全国に広く広まったようです。
恵方巻は、その年にあった方角を向いて一本丸ごと食べる事で、幸福や商売繁盛の運を一気にいただくということを意味している事が大きいようです。
恵方の方角は「十干(じっかん)」という干支が関係したものによって決まります。



節分と言えば豆まきをして鬼を追い払うというのが昔からの恒例行事ですが、最近では恵方巻を食べる人も多いです。2022年の方角は北北西です。
恵方巻きのあれこれ
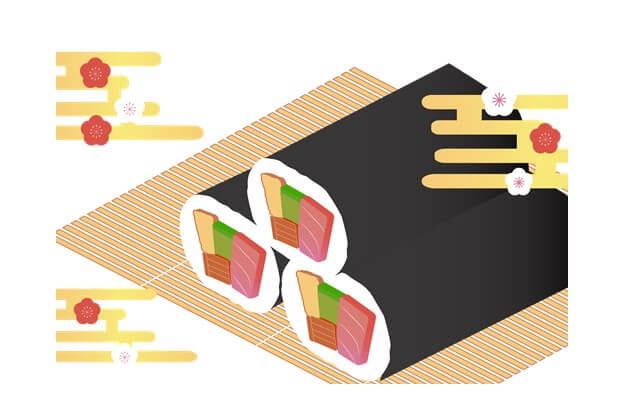
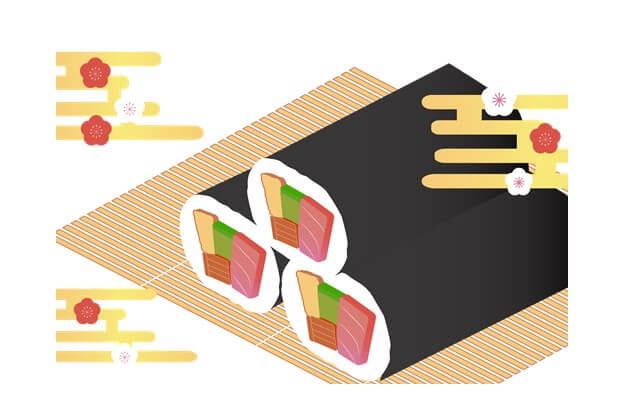
子供のころ、関東地方ではあまり見ることのないものだったと思います。
それというのも、元々の江戸時代から明治時代にかけての大阪の花街では「丸かぶり寿司」とか「太巻き寿司」と呼ばれることが多かったようです。
1989年に売り出して全国に広く広まった時に「恵方巻き」と名前をつけたのが広まったというのが恵方巻きという名前の始まりではないかと言われています。
「丸かぶり寿司」も「太巻き寿司」も七福にちなんだ7つの具を入れて巻くので、恵方巻も7つの具を入れたものが多いです。
食べる時の方向が決まっている
恵方巻には、決められた方向を向いて恵方巻をまるごと一本、一言も話さずに食べなければならないというルールがあります。
まるでゲームのようで楽しい行事ですよね。
一言も話さずに食べる理由は、しゃべってしまったり、途中で止めると福が逃げてしまうからなんだそうです。
恵方巻を食べる時の方角は4種類


恵方巻の恵方とは、陰陽道(おんようどう)で、その年の干支(えと)にもとづいて吉をもたらすとされる方角です。
その方角には「歳徳神(としとくじん)」と呼ばれる神様がいるといわれています。
歳徳神とは金運や幸せをつかさどる神様で、とても縁起のいい神様です。


歳徳神は毎年いる方角が違うので、恵方も毎年変わります。


歳徳神がいるとされる方角は次の4つのうちのどれかです。
- 「北北西」より少し北 = 壬の方角
- 「東北東」より少し東 = 甲の方角
- 「南南東」より少し南 = 丙の方角
- 「西南西」より少し西 = 庚の方角
今年の恵方は、どうやって決まっているの?
今年の恵方は西暦の下一桁によって決まります。
| 西暦の下一桁 | 該当する年 | 恵方 |
|---|---|---|
| 4・9 | 2024 | 東北東微東 |
| 5・0 | 2025 | 西南西微西 |
| 6・1 | 2026 | 南南東微南 |
| 7.2 | 2022 | 北北西微北 |
| 8.3 | 2023 | 南南東微南 |
恵方の微○とは、中国の方位で方角を示しているので、日本では少しずれた方角が正確な恵方になります。
東北東微東なら、東北東より少し東寄りが恵方です。
恵方はなんで毎年違うの?恵方の決め方は?


恵方の方角は、どういうふうに決められているの?


恵方は「十干(じっかん)」によって決まります。
十干とはいったい何でしょうか?
これには「干支(えと)」が関係していて、正式には「十干十二支(じっかんじゅうにし)」といいう古代中国が起源となります。
日本では物や種類や階級を示すときにも十干が使用されることが多いです。
たとえば、焼酎は甲類・乙類などといった種類がありますし、資格においても甲種・乙種などと表現されます。
契約書などでは甲・乙・丙という表記が使われています。
「干支(えと)」は十干と十二支を組み合わせたもので60種類あります。


60歳を祝う還暦は、干支の組み合わせをひとまわりして還(かえ)ったというお祝いのことになります。
十干と恵方の方角
最初に説明したとおり、恵方の方角は「十干(じっかん)」によって決まります。
それぞれの十干に対応する方角は以下の通りとなります。
| 十干 | 方角 |
| 甲(きのえ)・己(つちのと)の場合 | 東北東 |
| 乙(きのと)・庚(かのえ)の場合 | 西南西 |
| 丙(ひのえ)・辛(かのと)・戊(つちのえ)・癸(みずのと)の場合 | 南南東 |
| 丁(ひのと)・壬(みずのえ)の場合 | 北北西 |
例えば2022年(令和4年)の干支は寅(とら)です。
これは「壬寅(みずのえとら)」にあたり、十干は「壬(みずのえ)」となり、壬(みずのえ)が表す方角は北北西ということがわかります。
2023年(令和5年)なら癸卯(みずのとう・きぼう)なので、恵方は「南南東」になります。
恵方巻きっていつからあるの?食べる時の方角が毎年ちがうのはなぜ? まとめ


- 恵方巻きは、江戸時代から明治時代の頃に大阪の花街で節分のお祝いや、商売繁盛を祈って食べたのがルーツ
- 全国で広く食べられるようになったのは1989年に広島県で「恵方巻」を売りだしたのが始まりで、そこから全国に広く広まったという説が濃厚
- 恵方巻は、その年にあった方角を向いて一本丸ごと食べる事で、幸福や商売繁盛の運を一気にいただくとされている
- 2022年は「北北西」より少し北、2023年は「南南東」より少し南

コメント