今日は、以前に友人の職場にいた後輩Yさんの話になります。
Yさんは、まじめに業務をこなしていましたが、組織再編でBという部署に異動しました。
そこは簡単に言うと、生産に使う板の材料がまっすぐな平行な板になっているかどうかを検査して、
まがっていたら専用の工具を使ってまっすぐな板にするという部署でした。
いわゆる「技術」っぽいことが必要になる仕事です。
職人とまではいきませんが、それなりにノウハウのいる仕事でした。
そこに異動したYさんは、まったく仕事になじむことができません。
面倒見のいい先輩が3ヶ月くらい面倒をみてくれていたのですが、結局自分から退職していってしまいました。
今回は、そういう身体でおぼえる的なコツの必要な仕事で悩んだ時はどうすればいいか、という話になります。
一般的な「仕事の手順が覚えられない」ということについては、以前の記事を参考にしていただければと思います。

今回は、メモ術では対処の難しい「コツ」が必要で仕事ができない、先輩と同じ様にできない!というような時の対処方法になります。
仕事ができないと悩んだ時の対処方法
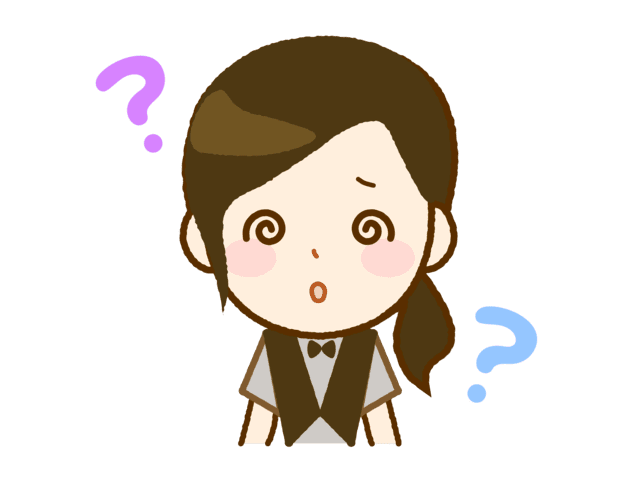
一般的な仕事ができない原因
- メモを取っていない
- わからないことをそのままにする
- 優先順位をつけるのが苦手、優先順位をそもそも考えていない
- コミュニケーション不足
となります。
どれも基本的なことですので、対処方法は以下のようになります。
- メモを取る
- 分からないことは質問して教えてもらう
- コミュニケーションを取る
- 仕事ができる人にアドバイスをもらう
メモを取る
メモを取るのは基本です。書いて覚える感じですね。
書いても、ほとんどは一週間もたてば忘れてしまいますが、見返せば思い出せます。まれにいる書けば一発で覚える人って素敵ですよね、うらやましいです。
分からないことは質問して教えてもらう
わからないことは素直に質問して聞きましょう。
そのまんまにしておくと、あとでたいてい(大小はありますが、一回限りの仕事でもない限り)問題になります。
同じことをなんども聞いたらまずいというのは中学生でもわかる基本ですので、メモをとるなり対処をした方がいいですね。
コミュニケーションを取る
挨拶もしない、ミスをしてもあやまらないという、自分の目を疑うような人間がいますが、そういう人に親切に仕事を教えようと思う人はふつういません。
コミュニケーションは円滑に仕事をする為にも必要です。
仕事ができる人にアドバイスをもらう
どうしてもできないなら、できる人にそう伝えて教えてもらいアドバイスを受けましょう。
一人でなやんでいても、ほぼ間違いなく時間の無駄ですので。
そういった対処方法をやっても、どうにもならない仕事ができない悩みの場合
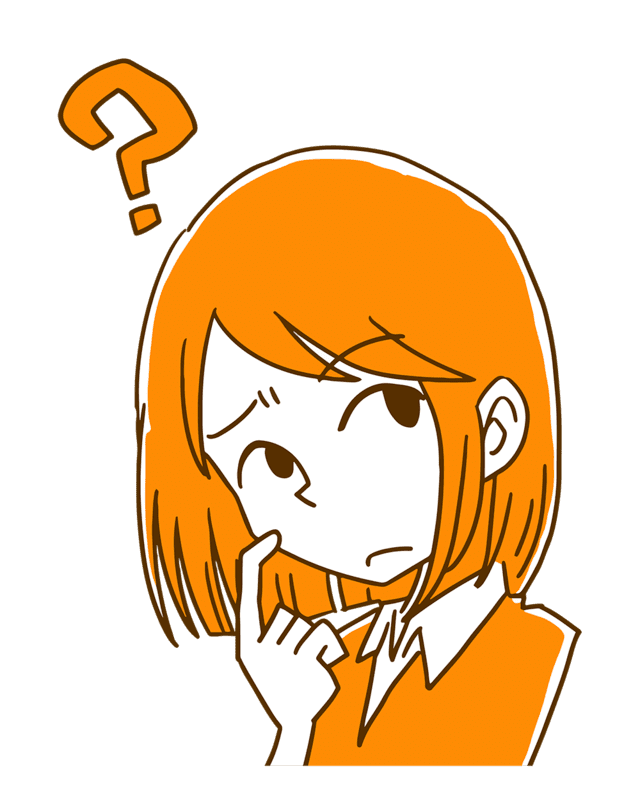
ここからは、メモを取った、質問もした、コミュニケーションも取ってるから人間関係にも問題はなさそう、アドバイスをもらってもどうにも真似できない事例です。
先述したYさんの事例になります。
Yさんは、ひととおり先輩にも相談して対処方法を試したのですが、どうやっても先輩と同じ仕事ができませんでした。
技術的、「コツ」が必要みたいな作業は、「見て」「聞いても」無理な場合がある
その仕事内容というのは、板の材料を検査して、まっすぐになっていない場合は専用の工具を使って板を矯正するという作業でした。
この時に作業が上手なら「カンッ!」という音がするんですが、下手だと「ガンッ」という鈍った音になったり、音がしなかったりするというのが、先輩や以前にその作業をした同僚の説明でした。
Yさんは、先輩のやるところを30分以上観察して同じ様に作業をします。
矯正工具というのは、品物を載せるフックが3つあるのでそこに材料を載せて、ひとつだけあるレバーを時計回りに回すと「カンッ」という音がして材料が曲がっていれば矯正されるという単純なものです。
Yさんは、先輩と同じ様に材料を載せます。
この載せる作業には特にノウハウもありません。同じ様に置くだけです。
ところが、「レバーを時計回りに回す」
たったそれだけの作業に職人チックなノウハウが潜んでいるのでした。
Yさんは先輩のときと同じ様に、レバーを操作してみます。
しかし、レバーを回すと「ガンッ」という音がして、材料はさらにひどく曲がってしまいました。
何度繰り返しても同じなので、ここでYさんは角度と回す速さに問題があるのではないかと思いあたります。
先輩にもう一度作業を見せてもらい、角度は11時の方向から3時の角度まで約1秒の速さでレバーを回しているのだとわかりました。
そこで、同じ様に11時の方向でレバーを一度止めて、そこから3時の方向まで同じ様にレバーを回してみます。
しかし、矯正工具は2時までまわしたあたりで「ガンッ」という音をたててしまい、音が違います。
そして矯正したものを検査してみると作業をする前よりも曲がってしまっていました。
相談しても、コミュニケーションをとっても、勉強しても無駄なケース
先輩に相談すると、バツが悪そうに「立ち方が悪い、足の置き位置が違う、手のひねり方が違う、姿勢が悪い・・」という具合なダメ出しのオンパレード。
以前にその作業をやっていた人に聞くと、「教わったとおりに練習したけど出来るようになるまで半年くらいかかった」というような話でした。
この一ヶ月あとに、Yさんは辞表を提出して会社を去っていってしまいました。
結局、練習してもこの作業がどうしてもできなかったのが原因なのは想像に難しくありません。
そういう作業の攻略方法
相談もした、質問もした、勉強もした、それでもできなくて、他の人はそれができるまで半年もかかった。
そんな仕事に友人が人員不足を理由に異動しました。
ここからは、そんな友人がこれを攻略した方法の話になります。
友人がやってみてもYさんと同じだった
友人はその部署の先輩について、Yさんと同じ様に仕事を教えてもらいます。
でも、結果はYさんとまったく同じでした。
観察して、教えてもらって、同じ様にやってみても、違うタイミングで「ガンッ!」という音がして、材料は作業をする前よりもひどく曲がってしまいます。
こんな場合、あなたならどうしますか?
友人がこの問題を解決した方法
友人はYさんと同じ立場になってからは、そこからは「ひたすら先輩の作業をしているところを観察」しました。
すると、先輩の使っている専用工具より、Yさんと友人の使っている専用工具の方が力が強くて、同じ様にそれを使っても先輩の専用工具より強く力がかかってしまうことに気が付きました。
友人は、先輩に専用工具を貸してもらい、先輩と同じ様にそれを使ってみますが、「ガンッ!」という音がしてうまくいきませんでした。
専用工具の違いには気が付きましたが、それだけが直接の原因ではありませんでした。
次に友人が目をつけたのは、先輩が言っていた「立ち方が悪い、足の置き位置が違う、手のひねり方が違う、姿勢が悪い・・」という説明でした。
この言葉がなにをあらわしているかと、友人はひたすら考えました。
その結果、専用工具を回す時に「力をかけるタイミング」や「力のかけ方」にコツがあるということではないかと推測しました。
先輩に相談すると、立つ時は足を30cmひらいて、肩をひらいて、右肘の位置は○○で・・・という具合に、いろいろと先輩と友人の作業の違いを指摘されます。
そのとおりにやってはみたものの、あいかわらず「ガンッ!」という鈍い音がして、結局うまくがいきませんでした。
この問題の解決方法
友人は、どういう原理で音がするのかをひたすら観察します。
すると、「カンッ」という音は、検査工具が材料に当たった時に音がしているのでなくて、検査工具が材料に当たってからほんの少し遅れて音が出ていることに気が付きます。
検査工具が材料をまっすぐにしようと接触した時に音がするのでなくて、レバーを回して検査工具が材料を叩いたあとにほんの0.1秒くらい遅れて「カンッ」という音がしていることに気がついたのです。
レバーを回して検査工具が材料を叩くと、レバーはそれ以上回らないので反時計周りに回して元の位置に戻します。
その時に「カンっ」という音がしていたんです。
友人はひたすら検査工具を試してみて、
「時計回りで9時の方向でレバーを止めて、2時半くらいまでレバーを回して、すぐにスッと反時計周りでレバーを戻す」と「カキンッ」という音がして、先輩と同じ様に作業ができることに気が付きました。
先輩の場合は「同じ様に11時の方向でレバーを一度止めて、そこから3時の方向まで同じ様にレバーを回してからレバーを戻す」と「カンッ」という音がします。
音も操作方法も違うのですが、検査してみても2つの材料の出来はまったく同じでした。
まとめ
身体でおぼえる的な仕事というのは、結構厄介なことがあります。
この友人の話は、わかりやすくする為に簡略化しているんですが、超簡単に言うと「レバーを回すだけ」なんです。
ですが、その「レバーを回す」だけのことなのに、説明すると難しいし「先輩と同じ様に同じ音がするように」という条件がつくと、できるようになるまで半年かかった人もいる、という話になります。
できないとなると数時間にわたる先輩からの指導が待っています。
その友人も、先輩と同じ様にやってもどうやっても同じ様に作業が出来ません。
そこで悩んだ末に、「同じ結果になるように作業するにはどうすればいいか」ということを試行錯誤しまくって、やり方は違うけど、結果は同じなんだからと開き直ったそうです。
やり方が違うと先輩から嫌味めいたことを言われることはあっても、作業のスピードは今までその作業に関わった人の中でもかなり早いほうなので、逆に 上司からはそれなりに評価されているそうです。
目的の為なら手段は選ばないという考え方
技術的、ある意味職人的に同じ様にできない場合、「どういう原理でそうなっているのか」ということをまず調べる。
そして、少しくらいやり方が違っていても「完璧をめざさないで、まず終わらせる」ということが必要です。
完璧をめざさないでまず終わらせるという考え方は、フェイスブックの創始者マーク・ザッカーバーグの言葉だと言われています。
先輩の言うとおりに「筋トレをして、出来るようになるまで半年間ひたすら練習する」か、
「どういう理由でそうなるのかを考えぬいて、細かいことは気にしないで、まずやってみる」のか、
あなたはどちらが正しい仕事の覚え方だと思いますか?
ということで、この記事はここまでになります。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
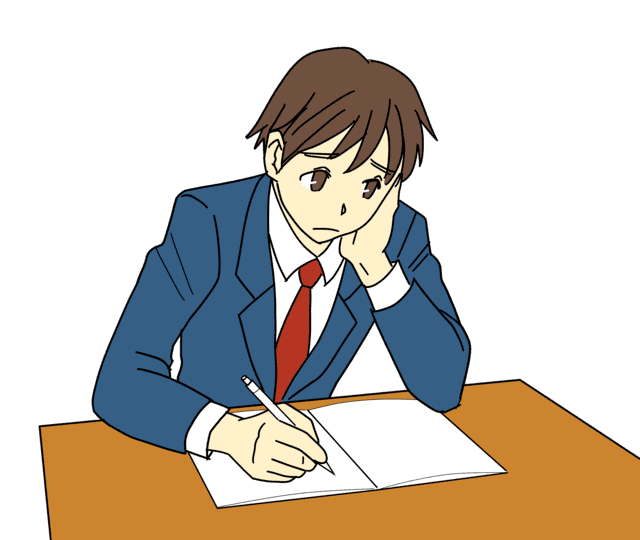
コメント